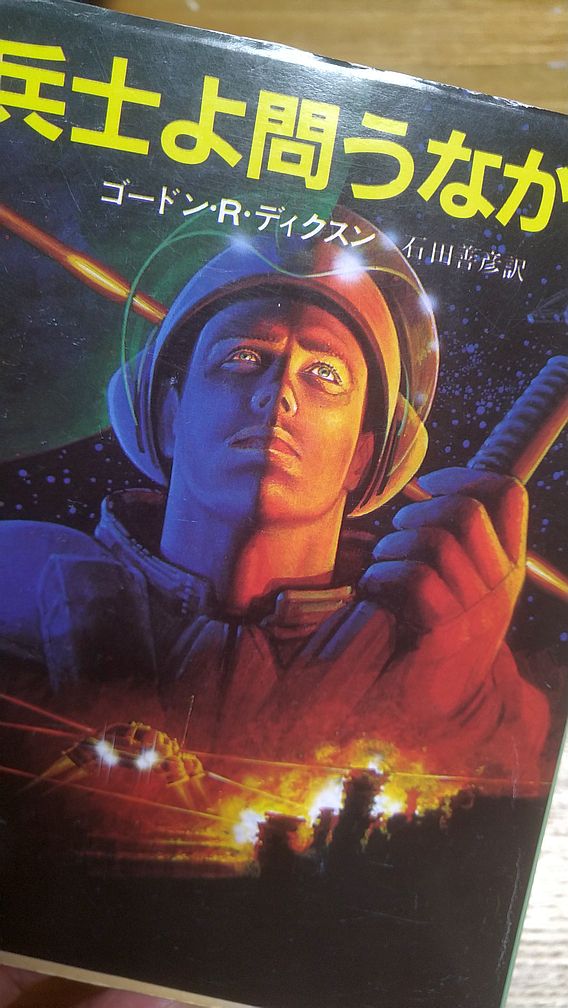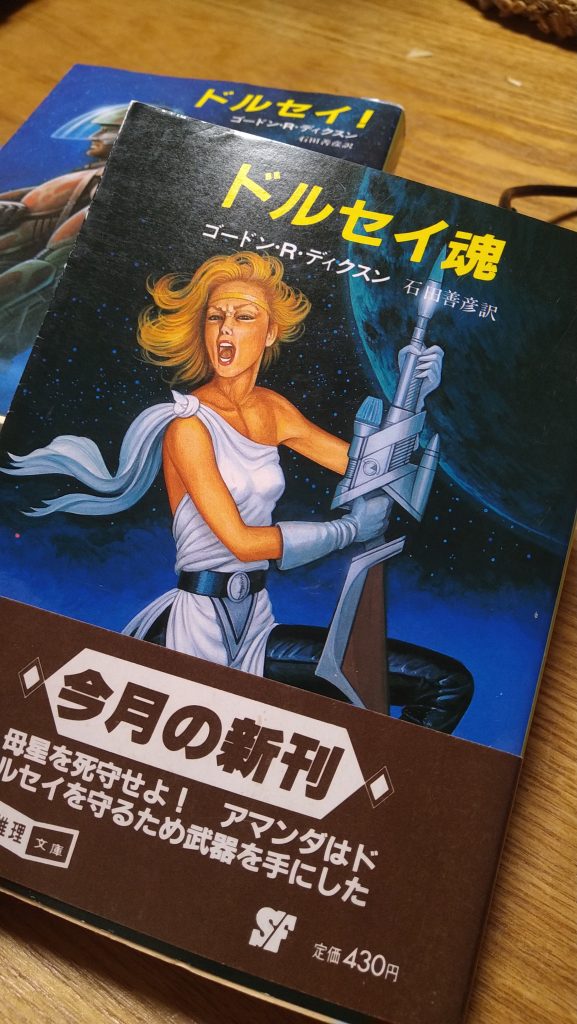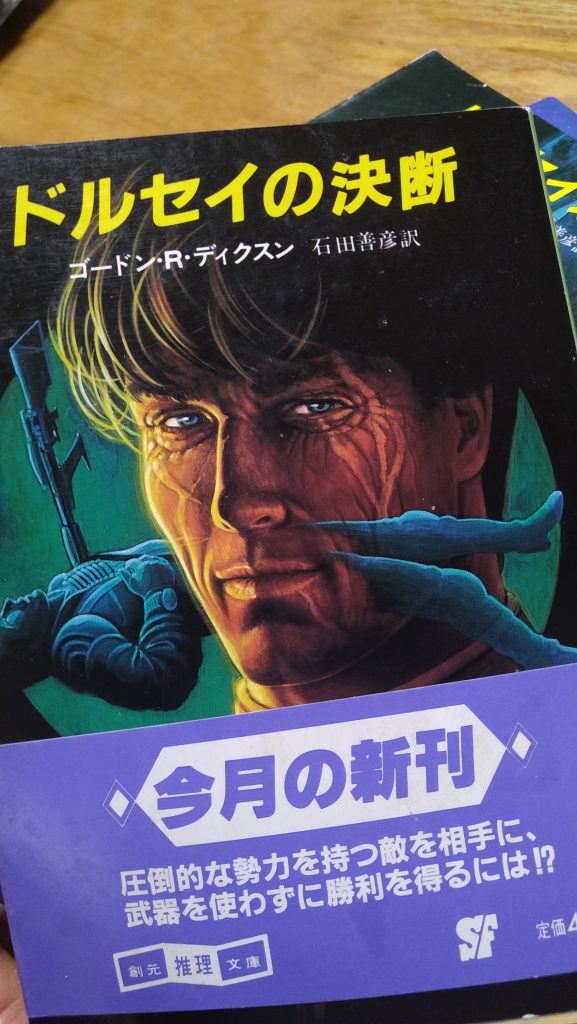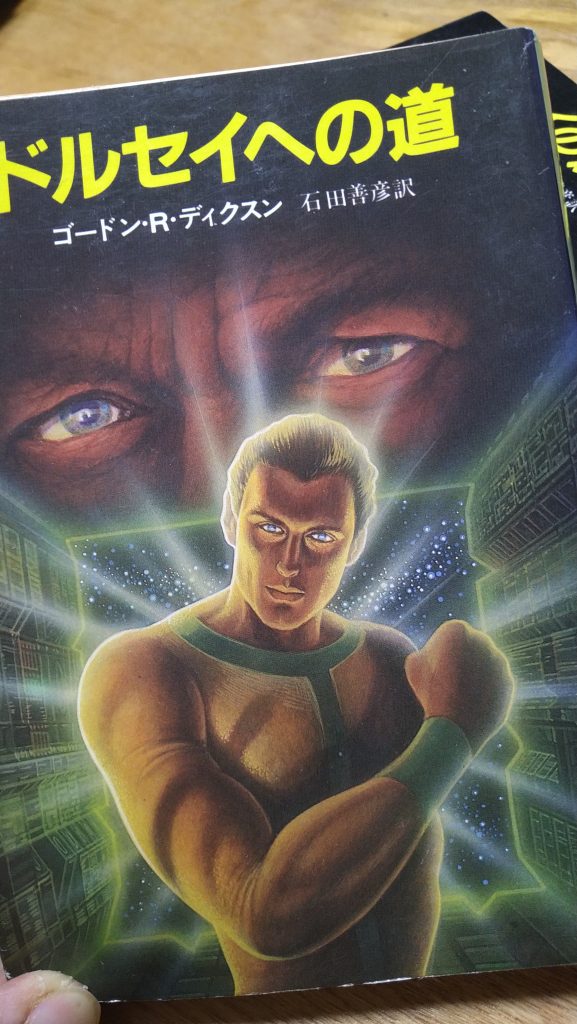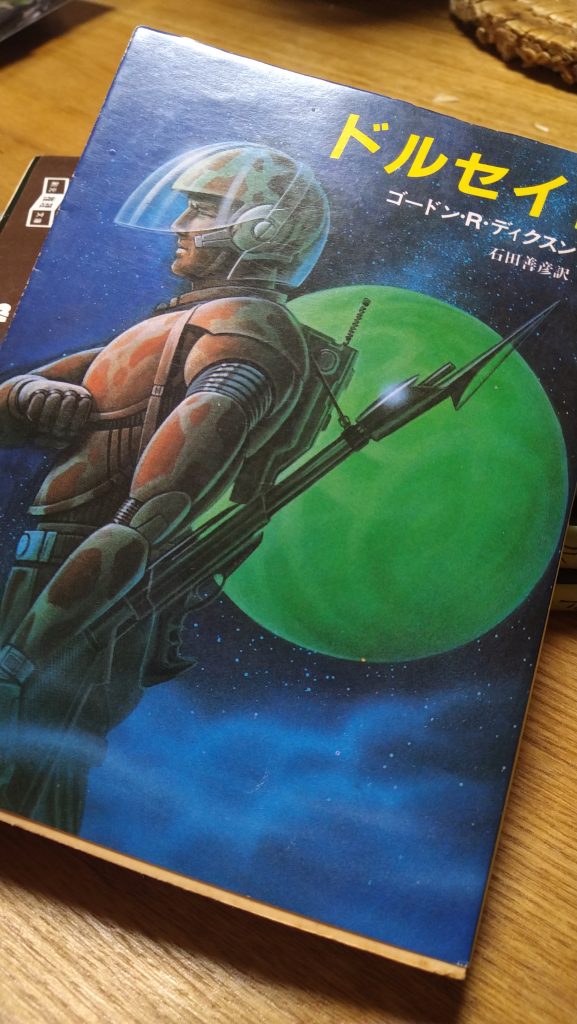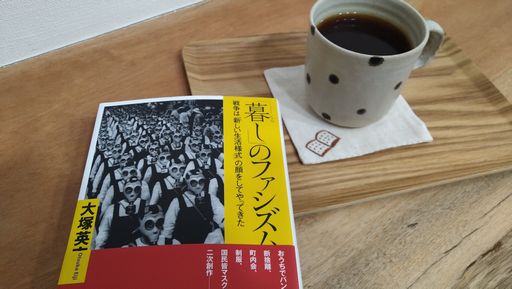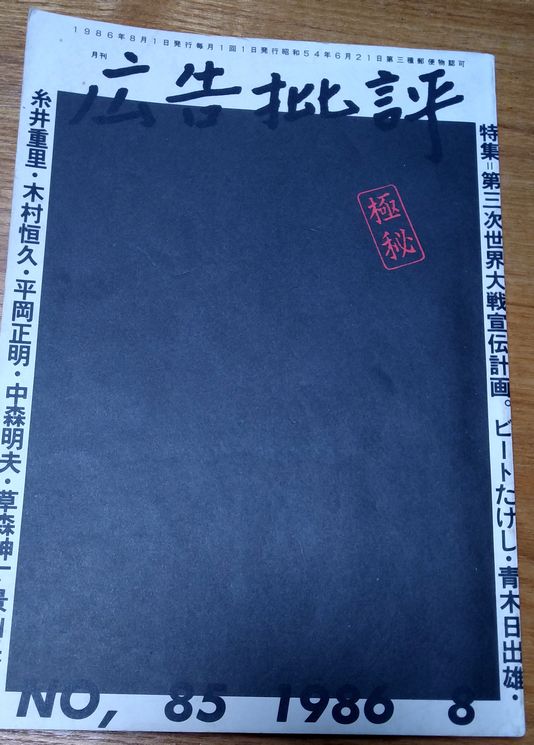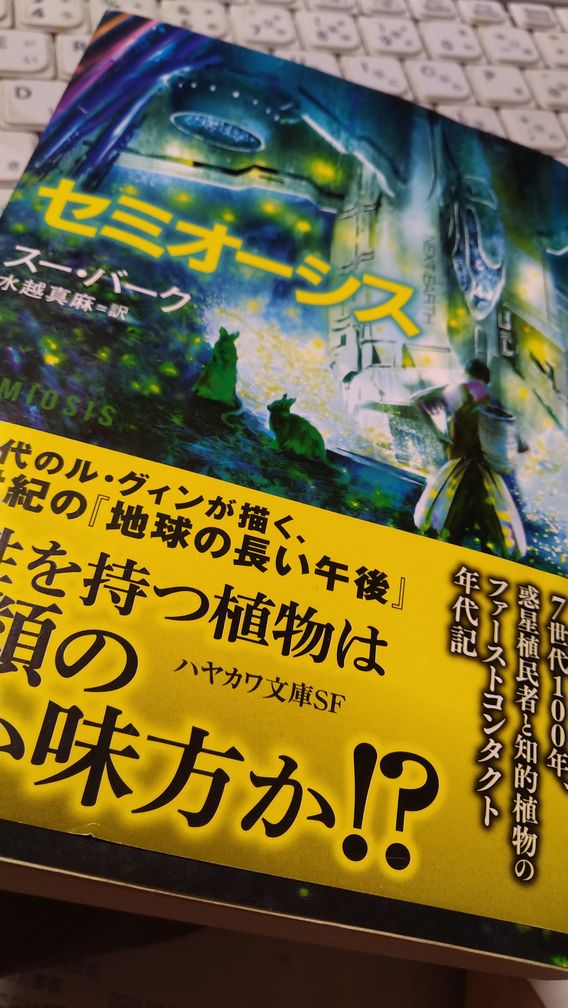THE ISLAND AND OTHER STORIES
ピーター・ワッツ
2004
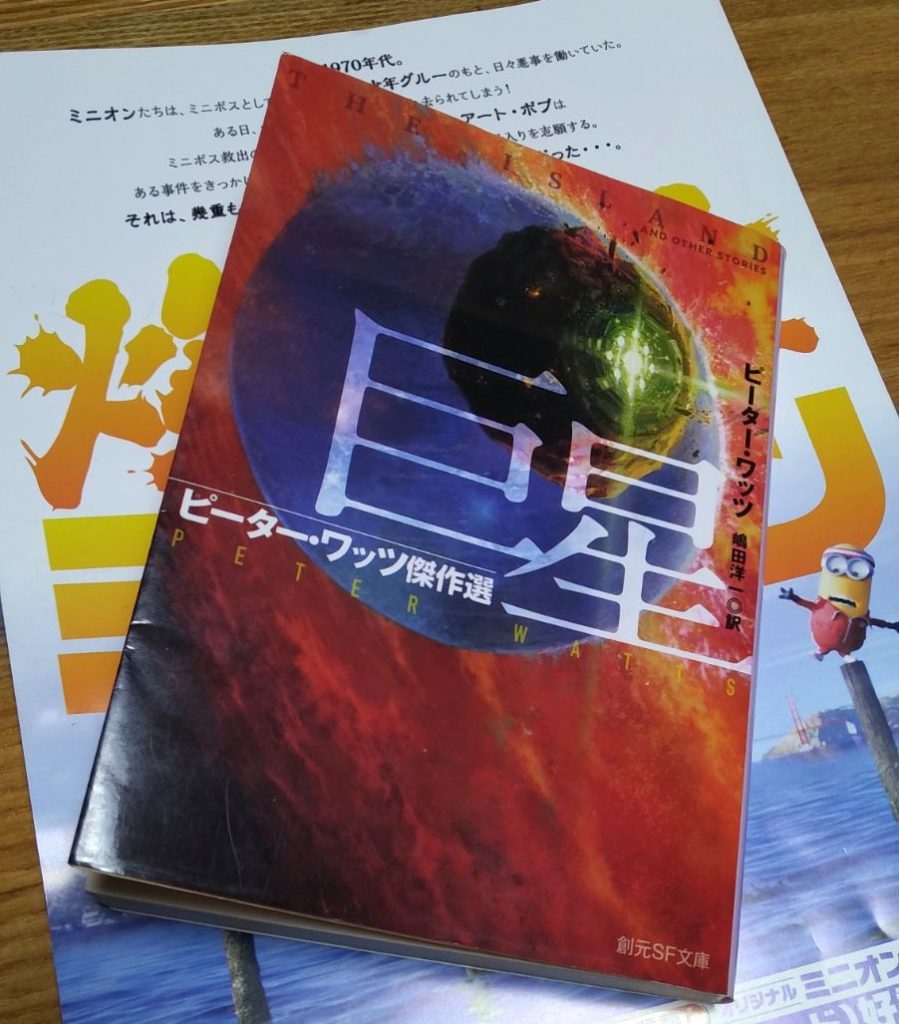
「ブラインドサイト」「エコープラクシア」のピーター・ワッツ短編集である。長編2冊は読んだのだが、もう一度読まないとなんとも書けないなあと感想には書いている。おもしろいのだが、「知性」「自由意志」といったものが全体の根底に流れているテーマなのでていねいに読まないと意図がつかめなかったりする。どうにもワッツはこのテーマに「神」というか「宗教」も挟んでくるのでこのあたりが難しいのだ。
しかし本書は短編集である。短編集の良いところはエッセンスがつまって、たいていがワンテーマだということだ。つまり作者の意図がはっきりしているし、はっきりさせたくないことであればそうとわかる。本書には11作品が収録されているが、そのうち最後の3作品はひとつの連なりになっているので連作中編といってもいいかもしれない。そして、「ブラインドサイト」や「エコープラクシア」にも連なるテーマを扱ってもいる。
「天使」AI兵器が作戦命令の上位司令からの個別手順変更をくり返されるうちに、自らの使命や機能について進化を遂げていくお話し。ちょっとブラック入っています。
「遊星からの物体Xの回想」名作映画「遊星からの物体X」です。ジョン・カーペンター監督版です。映画は人間サイドから描かれていますが、当然「物体X」にも動機と目的があるわけで、そちら側から書かれた作品。映画を見直す前にもう一度これを読んでから見たい。すごくすごく映画がおもしろくなりそう。(悪い見方です)。これを読むためだけでも本書の価値あり!
「神の目」これもブラック入っています。「内心の自由」とか考えさせるお話し。ある犯罪性向があって、それを簡単に判別できて、手術もなしに簡単に取り除けるとしたら、そういう社会を望みますか? 怖い怖い。
「乱雲」生命はどこから生まれるのか? どうやって生まれるのか? もし、地球の雲が生命となりその生存と繁殖のための活動をはじめたら地上はどうなるだろうか? 荒唐無稽な話だけど、やっぱりブラック入ってます。
「肉の言葉」AI技術を使って私そっくりに言語表現を反応する仮想人格をつくれるとしたら作りますか?主人公のウェスコットは「死」を研究する科学者。死んだ恋人キャロルの仮想人格と対話している。彼には現実に同棲している恋人のリンがいて、いまペットの猫が死んだ…。それがきっかけとなってリンはウェスコットの元を去るが…。ウエットウェアとソフトウェアの境界はどこにあるのかな。
「帰郷」深海での作業目的のために作り替えられた身体と精神。自ら理由も分からずにある場所へと導かれていく。そして、作り替えられる前の認識を少しずつ蘇らせるが…。ここでも「知性」とか「自由意志」がワッツのテーマであることをうかがわせる。ちょっと怖いお話し。
「炎のブランド」バイオハザードを起こした企業が、それを隠蔽していたがやがて発覚する。そのバイオハザードは組み換え遺伝子の水平伝播による人体発火現象。ブラックユーモアですが、現実にも公害と隠蔽の組み合わせはこれまでも起きていること。だから怖いのだけれど。
「付随的被害」「天使」はAI兵器の進化の話だったけれど、こちらは人間の兵士の反応を高めるため意識に上がる前に反射的に意識に上がり行動するであろう行なうインターセプトシステムを実験的に導入された兵士(ややこしい)の話。作戦行動中に民間人を殺してしまった。システムエラー?それとも、確かめずに殺す意志があったのか?ここでは「自由意志」と「道徳(倫理)」が語られる。そして、ブラック。こういう解決は好きではないが、作品としてよくできている。
訳者(解説者)によると、以下はSunflowers cycleシリーズの作品群で、時系列としては未訳の長編がホットショットと巨星・島の間に入るらしい。執筆順は全然違うのだが、この短編集では時系列で並べてある。親切。最初の「ホットショット」が少しわかりにくいため、冒頭に訳者による解説がつけられている。それにならって概要を説明すると、ワームホールネットワークを銀河系に構築するため小惑星を改造して時空特異点をつかった光速に近い航行を行なう人類のディアスポラ計画。通常はAIチンプが運行管理を行なうが必要に応じて人間の乗員が目ざめさせられる。5万年を超える片道旅行である。その恒星船のひとつエリオフィラの物語。
「ホットショット」太陽系の太陽は死にかけている。もちろんすぐではない。しかし、人類は地球を離れる必要があった。国連ディアスポラ公社によって祖父母の代から慎重に計画され育てられてきた恒星船の乗員。これから5万年以上の旅に出る、早熟の子どもたち。サンディもそのひとり。すでに自由意志など認められず、しかし、「自分で選択すること」を大人たちに求められる矛盾。サンディは選択の前に危険な観光体験である太陽ダイブを望む。太陽ダイブに使われるのは、サンディが乗り込む小惑星改造宇宙船エリオフォラの推進システムのプロトタイプ。ワームホールを利用した投石機だ。それで太陽から水星まで一気に帰ってくる。サンディはそこで未来をみつける。
「巨星」旅立ちから数百万年が過ぎていた。恒星船エリオフィラの内部でハキムと「ぼく」が目ざめさせられた。すでに赤い恒星スルトと巨大な氷惑星トゥーレと無数のデブリの星系内にいたが、エリオフィラが目的とするワームホールゲート構築がAIチンプによりおこなわわれているふしはない。そして、エリオフィラはスルトに衝突するコースをとっている。「ぼく」はかつてこの船で起きた「反乱」には加担せず、AIチンプとのリンクを唯一保っていた。ハキムはリンクを焼き切っている。だからぼくだけが知っていることも多い。そしてこの星系でのトラブルに気がついたAIチンプが「ぼく」を起こし、必要からハキムを起こしたのだ。エリオフィラとミッションを守るために。
未訳の長編の後日談。そして、ここでも「自由意志」と「認識」の問題が。
「島」サンディが起こされた。数千年ぶりのこと。そこには肉体年齢で20歳ぐらいのディクスがいて、自らを「息子」と名乗っていた。そして、AIチンプとリンクしている。目ざめさせられた星系では恒星の方から信号が届いていた。それは知性を感じさせるものであり、そのためにサンディが起こされたのだ。恒星をとりまくダイソン球的生命。それはワームホールゲート構築船エリオフィラに止まれと叫んでいた。ゲート構築を中断、移動し、ダイソン球的生命体を守ろうとするサンディ。ただかたくなに数億年前の地球で指示されたプログラムを果たそうとそれを拒むAIチンプと、AIチンプとリンクし、チンプに従うばかりのディクス。
AIチンプと乗員たちの果てのない抗争はいまだ続いていた。
永遠の時間の中で垣間見た彼らが構築したネットワークを通過する人類の末裔あるいは他の知的生命体。しかし、エリオフィラと接するものはなく、孤独のままに宇宙の熱死までこのミッションを続けるのだろうか。
サンディは自らの運命を呪い、そして運命に生きる。
ピーター・ワッツは「自由意志」や「意識」「認識」というところにこだわる。ほとんどそのために作品を書いているとしか思えない。そこのところがちょっとわかりにくくなるので、メインのストーリーが複雑に見えてしまう。メインのストーリー展開と、そこで繰り広げられる「自由意志」の問題を頭の中で整理して切り分けながら読むと、とても面白いことに気がつく。短編だからこそ、わかること。長編だと頭がぐちゃぐちゃしてくる。心して長編も読み直したい。
(2022.4.18)