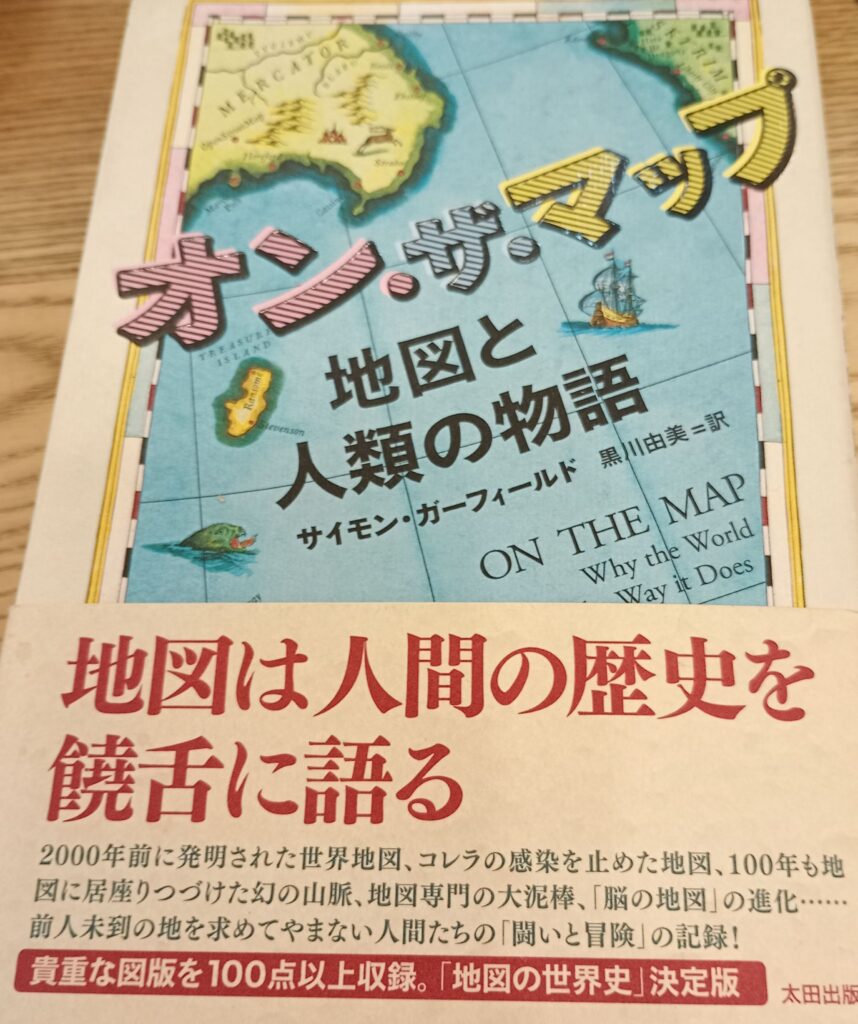A BRIDGE OF YEARS
ロバート・チャールズ・ウィルスン
1991
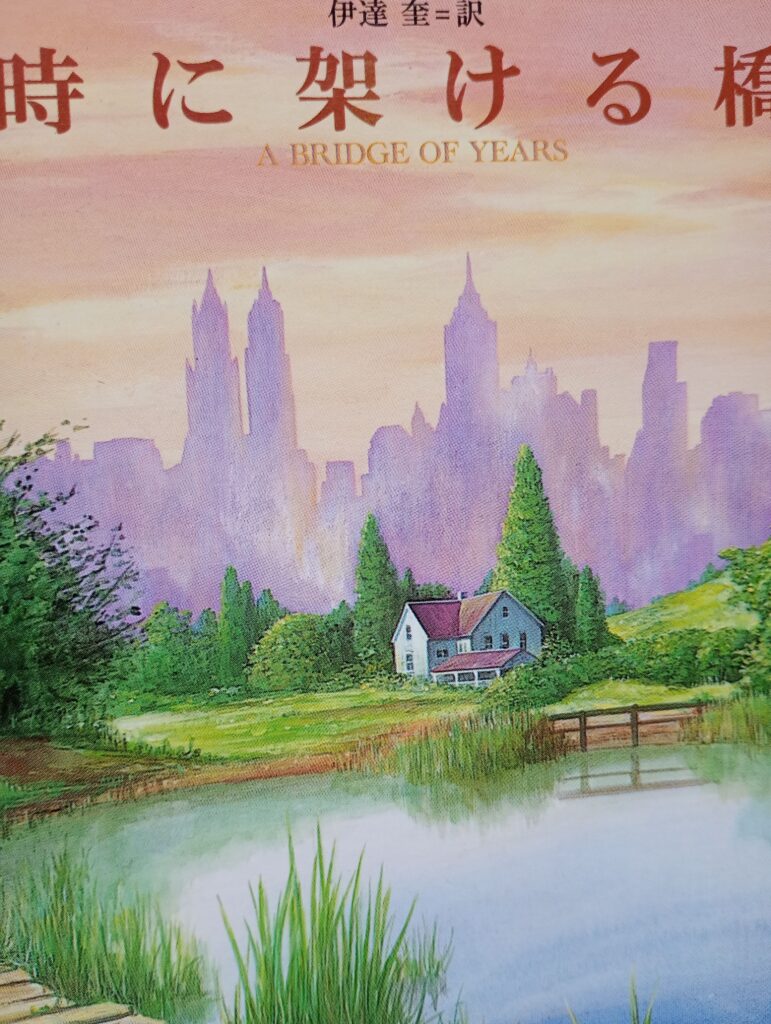
すっかり忘れていた。好きな作家なのに。ごめん、ロバート・チャールズ・ウィルスン。「時間封鎖」「無限記憶」「連環宇宙」の作家じゃないか。タイムトラベルものを敬遠する傾向があるからといって、なんでこの作家の長編を読み損ねていたのだろうか。反省。やっぱりおもしろいじゃないか。わかりやすくて、おもしろくて、読みあきさせない。しかも、後の「クロノリス」や「時間封鎖」三部作、「楽園炎上」にもつながるような小道具としての「時間」の使い方と、登場人物の受け止め方がじつにすばらしい。
舞台は、1989年のベルタワー。アメリカ北西部の太平洋岸にある霧の多い小さな町である。主人公のトム・ウインターは生まれ育ったこの町に戻ってきたところだった。妻と別れ、仕事を失い、兄夫婦の暮らすこの町へ。そこで、トムは森の中の古い一軒家を紹介されて購入する。物語はそこから動き出す。
さかのぼって1979年。その家に住むタイムトラヴェラーのベン・コリアーは21世紀末から来たとおぼしき襲撃者によって殺され、森の奥の小屋の中にうち捨てられた。それ以後、誰も住むものなく、公売にかけられ、トムがその家を買ったのである。10年の間だれも住んでいなかったのに、家の中はとてもきれいで塵ひとつなく、そして。
もうひとつの舞台は1962年のニューヨーク。トム・ウインターは時と空間を超えてきた。そこで彼はおせっかいで声の美しい女性のジョイスに出会う。妻のことを忘れられないでいたトムにとって、ジョイスは輝いていた。
ということで、1979年の凄惨な襲撃事件をプロローグとして、「自分探しさえもできていない、少年の頃に時間を置き忘れてしまったかのような迷える青年トム」の物語がはじまる。1989年の田舎町の郊外と、1962年の発展する大都市ニューヨークのはざまでトムが他者とどのように接しふるまうのか。それを基軸にしながらも、タイムトラヴェラーの秘密、襲撃者の謎、そこから垣間見える時間をあやつる未来の姿。いく人かの人生が交差し、変わっていく。それは必然なのか、それとも時を行き来したことによる改変なのか。
主人公の1989年を生きるトムは、時間移動技術に偶然遭遇しただけであり、「そこにあるから使う」だけの存在である。その技術的な内容やタイムパラドックスについてはトム自身は知りようがない。知らなくて使っているから、トラブルにも巻き込まれるが、そもそも何かのスイッチを押したり制御したりできるものでもないから、トラブルも極めて人間的なものだったりする。そういう「状況に置かれた」というのがポイントなんだろう。
背景に未来の世界、未来の人類、未来の技術という大きなものを予感させながら物語は、80年代末と、1960年代初頭の独特の空気感をまとって進んでいく。このバランス感覚が作者のお得意とするところで、のちの作品群に昇華されていくのである。