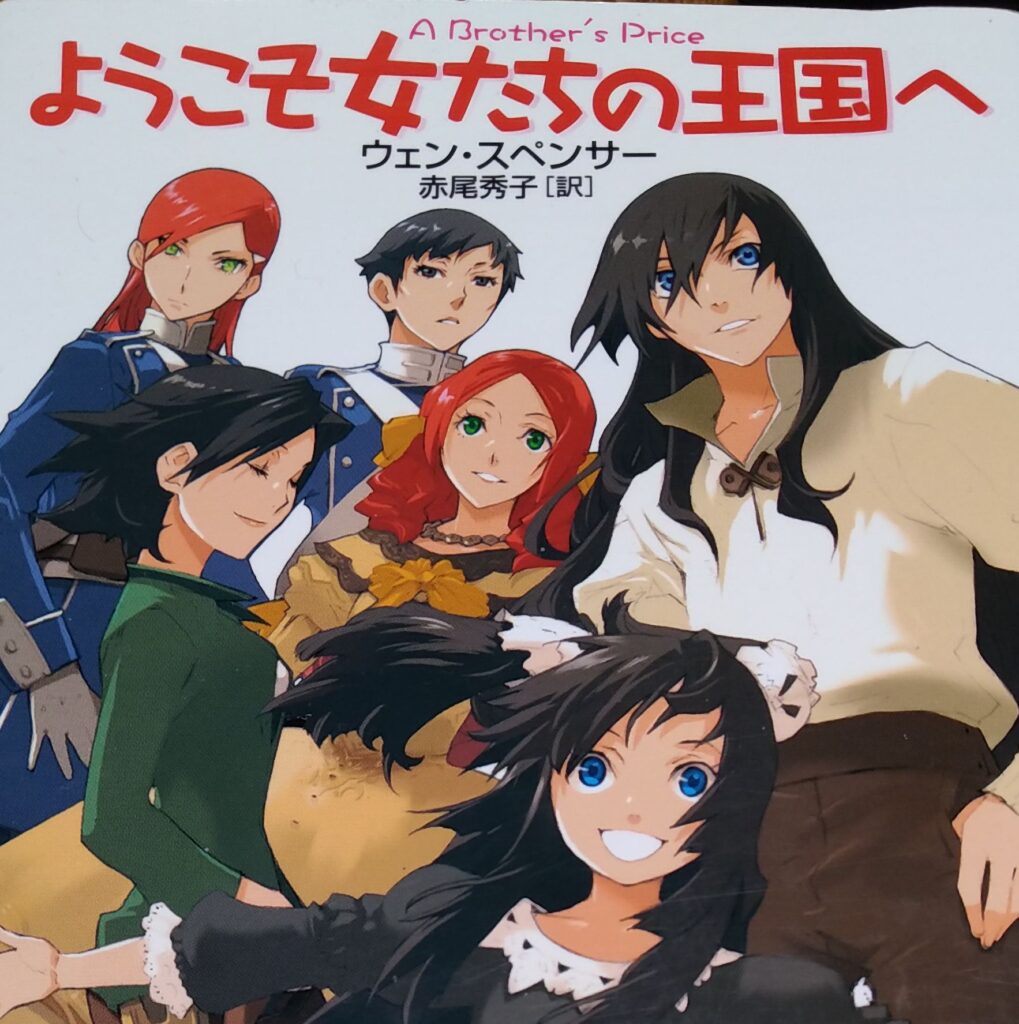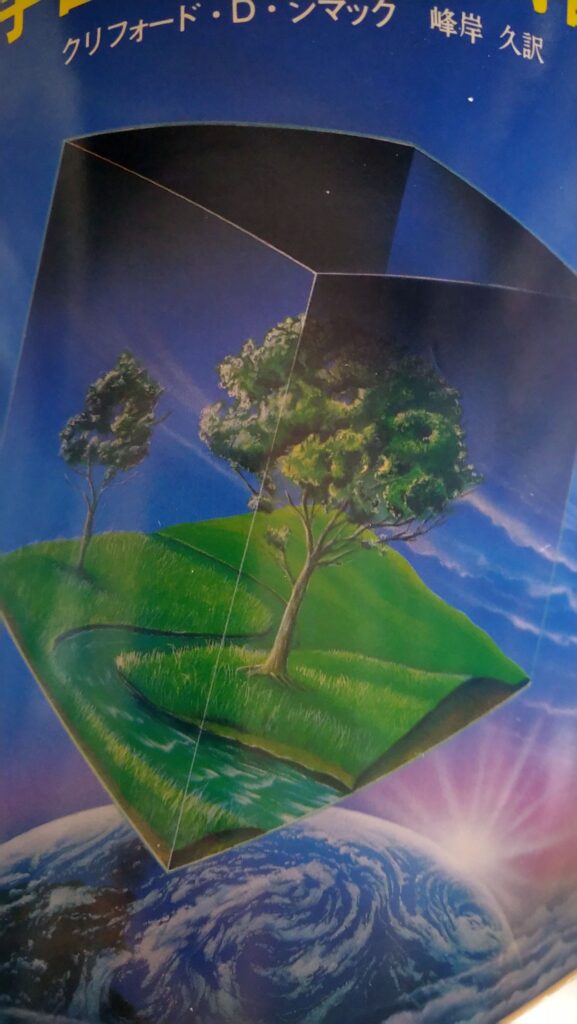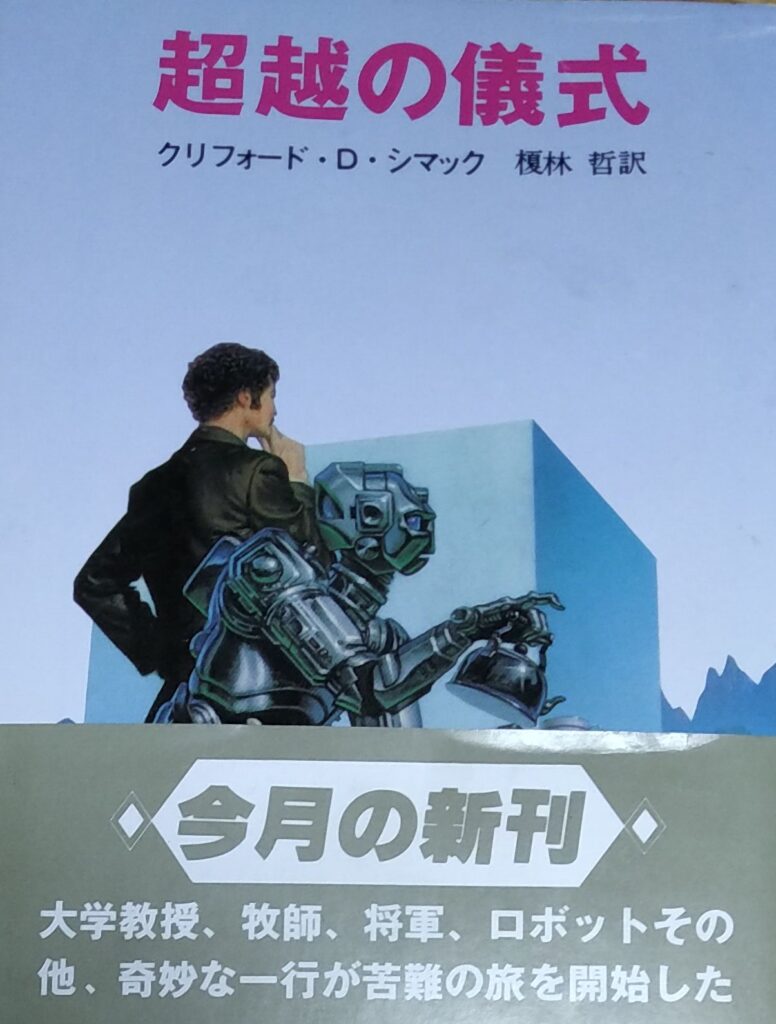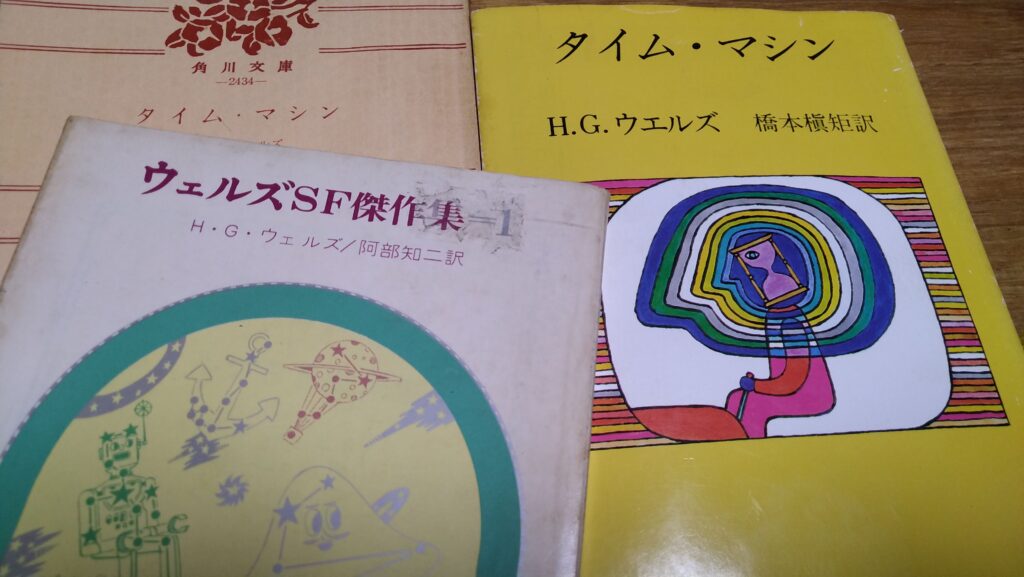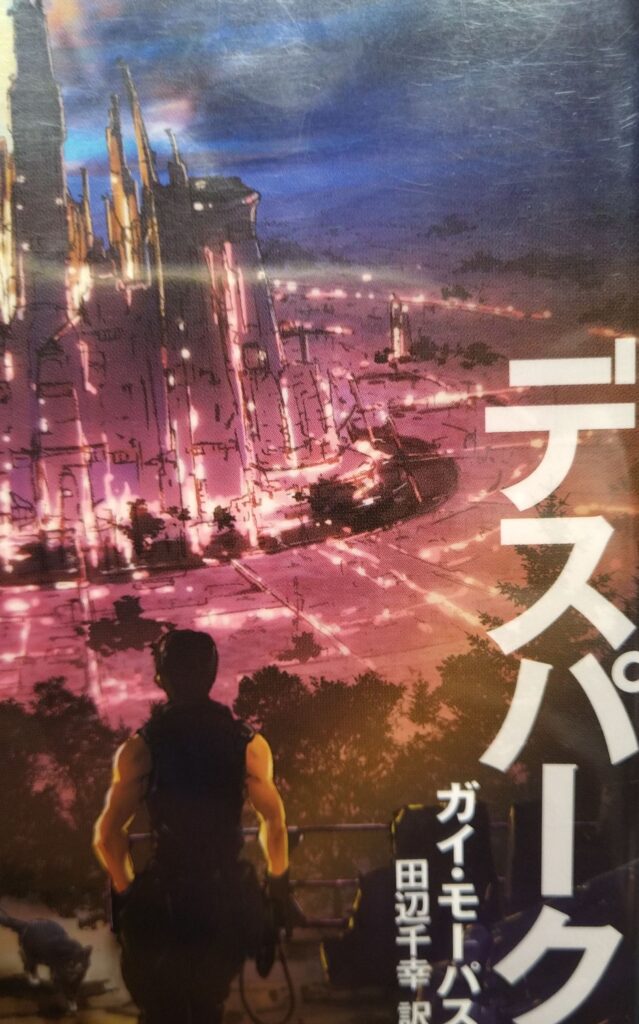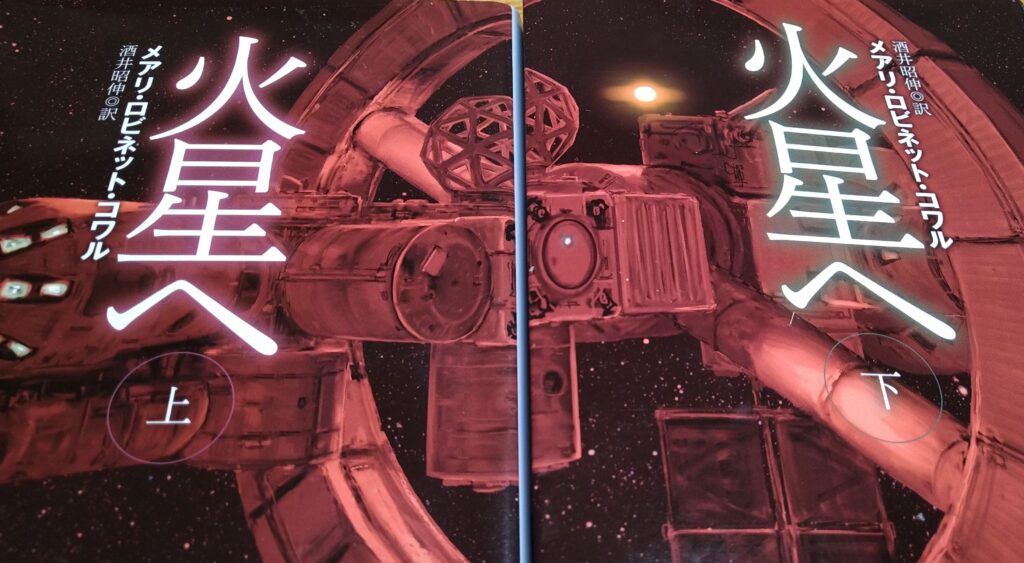広島市タカノ橋商店街にあった、夢売劇場サロンシネマ。1980年代当時、同所にはサロンシネマとタカノ橋日劇のふたつの映画館があり、私が広島を離れた後、1994年にタカノ橋日劇がサロンシネマ2と名称を変えたらしい。2014年には市の繁華街中心部の八丁堀に移転したという。
映画館がひとつだけしかなかった町から出て、広島に来たとき、まっさきに頭に浮かんだのは「映画見放題」という言葉だった。とにかくたくさん映画を見よう、そう心に決めた。すでに「レンタルビデオ(VHS)」という商売ははじまっていたが、当然のことながら大学1年の頃はテレビもなく、2年以降もテレビはあったもののビデオデッキを持っていたのはごく少数の友人たちだけであった。そんな時代のことだ。
そんなサロンシネマの一番のお楽しみが、定期的に開かれる FILM MARATHON(フィルムマラソン/フィルマラ) である。土曜日の夜遅く、21時半の開演を前にわらわらと少しゆるめの過ごしやすい格好をした若者やおじさんが灯りのほとんど消えたタカノ橋商店街に集まってくる。100席のサロンシネマには、時には当日券を求めてやってきて満席と聞き、がっくりとした人に、立ち見でよければいいよ、とささやく声も聞こえたりする(時効だからね)。立ち見と言っても通路に座布団を敷いてくれるので安心だったり。
学生時代の4年間を中心にかなりの回数を行ったのだが、何回行ったのかは覚えていない。ただ、先日、実家の片付けをしていたら、当時のパンフレットがいくつか出てきた。
#32 1983年「SF&ホラー怪作特集」
はじめてロッキー・ホラー・ショーの洗礼を受けた記念すべき日。早くから来た常連はクラッカーをもらっていて、くだんのシーンでパパパパパン!と。映画は劇場でみんなで見るものだ。?ムービーは、…たぶん フレッシュ・ゴードン(1974年、マイケル・ベンベニステ監督)。「フラッシュ・ゴードン」のパロディポルノ映画。どの作品も最高にくだらない。
#33 1984年1月21日、28日(土)「ヒロイン特集(PART3)」
ナスターシャ・キンスキー最高!長い長い映画です。オードリィ・ヘップパーン最高!朝5:30からオードリィの洗礼を受けると、最後には涙腺が崩壊します。
#34 1984年3月10日、17日(土)「アカデミー作品賞特集」
この回は行っていないと思う。ちなみに全席指定券1400円だと。
#36 1984年「ヨーロッパ傑作特集PART2」
ロバート・デニーロ、イブ・モンタン、マルチェロ・マストロヤンニの3連発。濃い男たちの濃い映画3本。とくに最初の「1900年」は2部構成5時間の大河ドラマ。
#37 1984年6月2日、9日(土)「ルキノ・ヴスコンティ監督特集」
見たんだよなあ、たぶん。記憶にない回だがパンフレットはある。ただ同時期に日中のフェアで「ベニスに死す」「地獄に墜ちた勇者ども」もやっていて、こちらは見た記憶があるので見たのだろう。美しいけど映像がくどいのよ。
#38 1984年7月14日、21日(土)「SF傑作特集」
パンフレットはないが、この回は見ている。記憶がはっきりある。やはりSF作品が好きなのだ。ダーク・クリスタルの人形の微妙さ加減にはじまり、暗い気持ちになる2作を経て、楽しい気持ちい切り替え、最後はじっくりとハリソン・フォードとルトガー・ハウアー、ショーン・ヤングの演技に入り込んだのであった。ブレード・ランナーは公開時に映画館では見ていないので、たぶんこの時が初回。その後何回も何回も見たけれど。
#39 1984年8月18日、25日(土)
こちらは#37のパンフレットに書かれていた予定。見ていないが、日中にデビット・ボウイの2作(ジャスト・ア・ジゴロ、地球に落ちてきた男)は見ている。格好良いよ、ボウイ。
#42 1984年たぶん10月「ベトナム後遺症映画特集」
とても印象深い回。正直なところ「ブルーサンダー」の印象が残っていないのだけれど、それだけ他の3作の衝撃が大きかったのだ。監督もすごいが、マーロン・ブランド、シルベスター・スタローン、ロバート・デニーロである。3人が3人ともちょっと狂気のある主人公を演じる。明け方のデニーロは怖いよ。
#43 1984年11月10日、17日(土)「西ドイツ映画傑作特集」
まだドイツが統一される前のこと。ドイツは西ドイツと東ドイツに分断されていて、東西冷戦米ソ冷戦の最前線になっていた。ナチスドイツから民主化された西ドイツには深い戦争の傷跡があり、それが新しい文化を生んでいく。2~4作目はすべて戦争映画である。そして冒頭の「フィツカラルド」の衝撃! 映画の内容も衝撃的だが、なんといってもドイツの名優、主演のクラウス・キンスキーの狂気。よくよく見れば、ナスターシャ・キンスキーにはクラウスのおもかげがある。父ちゃんだ。という衝撃。
#44 1984年12月15日、22日(土)「日本映画青春傑作特集」
#43のパンフレットから。洋画館だけどこういうのも遠慮なくやるのがサロンシネマの良いところ。「家族ゲーム」と「竜二」は日中に見た記憶がある。森田監督の松田優作はすごかった。
#45 1985年1月19日、26日(土)「ヒロイン特集PART5」
こちらも#43のパンフレットから。「愛と哀しみのボレロ」はとても長い映画だけど、いまでも本気で見る価値のある映画。音の良い環境で見たい。
#51 1985年7月13日、20日(土)「たまらなく好きなのヨ 映画特集」
ロバート・レッドフォード作品にはさまれたマイケル・ダグラスと、ハリソン・フォード。この回、結果的には全部バーブラ・ストライサンドが持っていったと思う。
#52 1985年8月16日(金)、17日(土)「東宝アイドル映画特集」
#51パンフレットから。夏休みだねえ。
#53 1985年9月14日、21日(土)「ヒロイン特集PART6(女優賞編)
#51パンフレットから。
#54 1985年12月14日、21日(土)「ホラー!見てごらんPART4SFXファンタジー編」
私はホラーが苦手だ。SFは好きだが。リンチのイレイザー・ヘッドで出てくるビルのつくりつけスチームヒーター(デロンギの電気のような形状のやつ)のシューシューいう音が耳について、いやあ怖かった。ほかの印象を払拭するぐらい怖かった。ちなみに、私は後にフィレンツェでモデルとなった「赤ん坊」のオリジナルの彫刻をみることになる。
#55 1986年1月11日、18日(土)「ごちそうさま!のフルコース 映画特集」
#54のパンフレットからだけれど、この回見てる。
#56 1986年2月15日、22日(土、予定)「ヒロイン特集PART8 ナスターシャ・キンスキー特集」
#54のパンフレットから。見てないな。でも、「パリ、テキサス」はよかった。
#64 1987年1月31日、2月7日(土)「青春映画特集」
良かった!たぶん大学生最後の頃、見るべき映画を見たという感じ。この回はほぼロードムービー特集だったと思う。ファンダンゴはいまでも定期的に見たくなるし、ジム・ジャームッシュ監督を知ったのも嬉しい。スタイリッシュで良かった。でも?ムービーはなんだったっけ。
#65 「ウディ・アレン・フィルム・フェスティバルPART2」プラス1
#64のパンフレットから。
ここからは、この期間にサロンシネマで上映されていた映画のうち、手元にあるパンフレットに載っている作品のリスト。
マイ・フェア・レディ
こうやってみると私の映画鑑賞人生の大きな要素を占めている。タルコフスキーに浸れたのもここのおかげ。いまだに「ノスタルジア」は見てしまう。